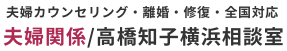夫婦の関係が悪化して苦しい毎日、「進む道はもう離婚しかない」と覚悟を決めた方や 相手から離婚を申し立てられ不安な方も含めて、日本での離婚の方法で一番多い協議離婚について知っていただければと思い記載します。
ふたりで決める協議離婚の知識

夫婦の話し合いにより、お互いに離婚に合意して別れる方法です。
裁判所が関与しませんので、離婚理由も離婚条件も夫婦ふたりが合意出来れば何も問題ありません。
夫婦が合意したうえで、本籍地・住所地の市区町村役場に「離婚届」を提出し、受理されれば成立します。離婚届には夫婦ふたりの 署名捺印と証人2名の署名捺印が必要です。証人は成人であれば誰でもよく、双方からひとりずつという決まりもありません。
協議離婚の場合、親権者や養育費、財産分与・慰謝料などお金のこと、面接をどうするかなど子供のこと、年金分割など、 自分たちで取り決めておく必要があります。未成年の子供がいる場合は親権者を離婚届に記載しなければ受理されません。 また、離婚協議書を作って、後々、揉めることのないようにしましょう。離婚協議書は自分たちで作成することも出来ます。
離婚に際する取り決め・離婚協議書記載事項
親権者・養育費
未成年の子供がいる場合には、離婚後、親権者をどちらにするか決めなくてはなりません。親権者となった親は親権に基づき、 未成年の子を監護養育します。子供の監護にかかる費用を分担し、親権者とならなかった親は子供の養育費を支払い、 親としての責任を果たしていきます。養育費の額は話し合いで決めますが算定表を参考に決めることもあります。
※参考記事:親権について ・養育費について (親権者と監護権者を分けたいと考える方はコチラもご覧下さい)
面会交流
子供は両親からたっぷりの愛情をもらって育つのが良いと思います。親の事情で離婚となってしまったら、特別な事情がない限り、 子供と離れて暮らす親との交流は頻繁で自由がいいと思います。
片親になったことで不安を抱えてしまうお子さんは大変多くいらっしゃるので、 子供が何も言わないから大丈夫と決めつけない ようにしましょう。子供は親の顔色を見ていますし、一緒に暮らす親が不機嫌になるのを 避けたいと思っていますので、離れて暮らす親に会いたいと言えない場合が多々あることを忘れないで面会交流についての取り決めをしましょう。
※参考記事:面会交流について
慰謝料
不倫などの不貞行為・暴力など離婚の原因を作った方が精神的苦痛を与えた方へ支払う損害賠償です。 性格の不一致や価値観の相違などの離婚理由では請求することが難しいと言われています。
※参考記事:慰謝料について
財産分与
同居してから別居するまでに夫婦の協力で得た財産を分けます。離婚理由がどうであれ、現在では5対5と 公平に分けることが基本です。結婚前に貯めたお金や親からの相続などは共有財産ではありませんので分与しません。
※参考記事:財産分与について
年金分割
婚姻期間中の厚生年金の掛け金を夫婦で半分ずつにまで分けることが出来ます。年金記録を分け、 それに従って年金の支給を受けることになります。
手続きは離婚してから、2年以内に行います。年金分割には2種類あって、 合意分割と3号分割とがあります。年金分割についてはやや手続きが複雑なので、日本年金機構の年金事務所に問い合わせ ながら行うのがいいと思います。
特に熟年離婚の場合、年金分割のよる年金額の影響は大きいですね!
国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方 の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
第3号被保険者で あっても平成20年3月31日以前の分は合意分割になります。3号分割のみの方は、あえて相手方に分割することを伝え なくてもよいと思いますし、離婚協議書に記載する必要もありません。手続きも一人で行えます。
3号分割以外の年金分割です。夫婦間で分割する割合を合意して手続きをします。この割合については、最大の0.5が一番多く、 平成26年の資料では約96%が0.5に定めています。夫婦で合意した割合を離婚協議書に記載します。
※参考記事:年金分割について
公正証書作成のおすすめ
作成した離婚協議書を公正証書にしておくと、より安心です。離婚協議書やそれを公正証書にすることは法律上の 義務ではありませんが、離婚後に金銭のトラブルが発生する可能性が少しでもある場合には必須と捉えましょう。
養育費や、その他慰謝料等、分割での支払いがある場合は、公正証書の作成をおすすめ致します。公正証書とは、 法律の専門家である公証人が作成する公文書のことです。公正証書を作成しておけば、いざという時に裁判を起こさず強制執行する ことが出来ます。公正証書は強制執行機能を備えている強力な証書です。
公正証書が養育費の支払いが滞らないためのブレーキにもなります。また、年金分割の割合を記載しておけば年金機構の手続きに ふたりで行く必要もありません。
また、どうしても親権者と監護権者を分ける場合、離婚届は親権者のみの記入になりますので、公正証書にその旨を記載して トラブルを避けることが良いと思います。
公正証書は作成した離婚協議書を公証役場に持参し依頼します。受け取る時には、夫婦ふたりで行き署名押印が必要です。 (代理を立てたい時には、事前に申し出なければなりません)離婚届を提出する前に作成しておきましょう。